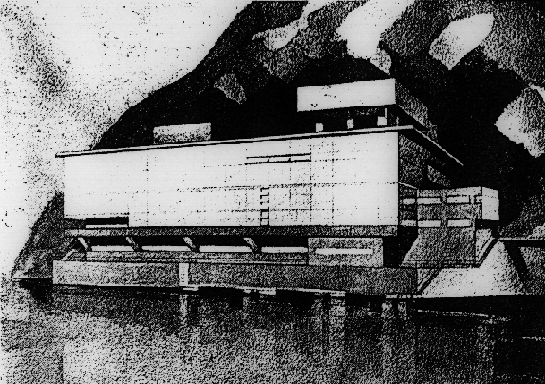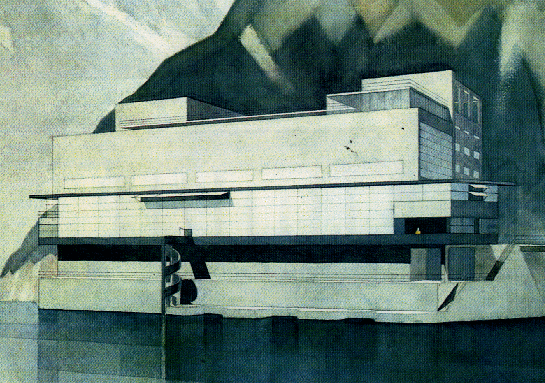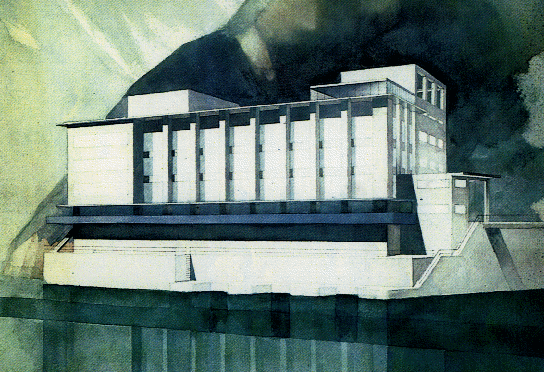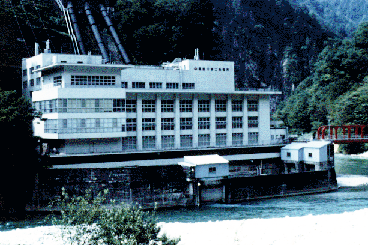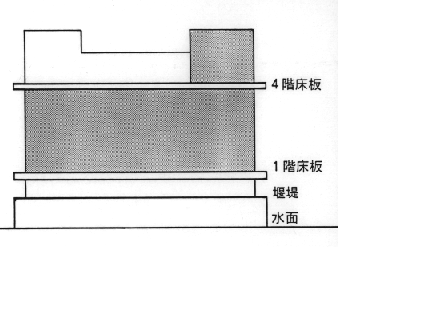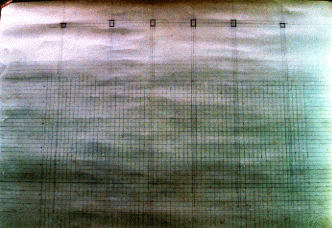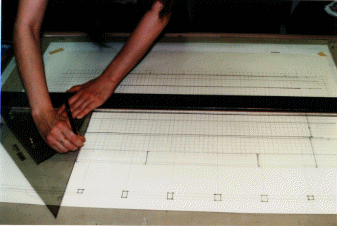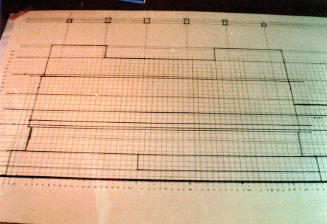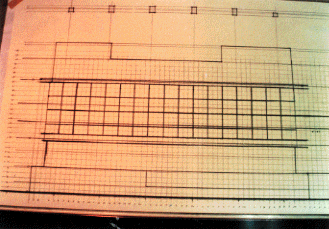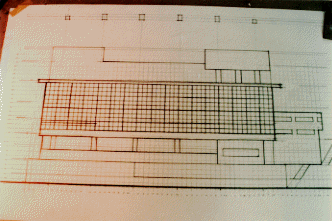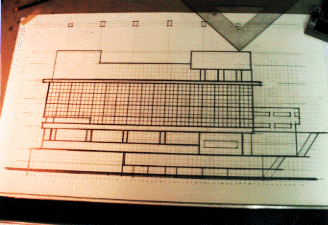3.デザイン-ファサードにおける設計手段の分析
(1)ファサードにおける思考プロセスの仮説
◎仮説Ⅰ:モデュールの意識の存在
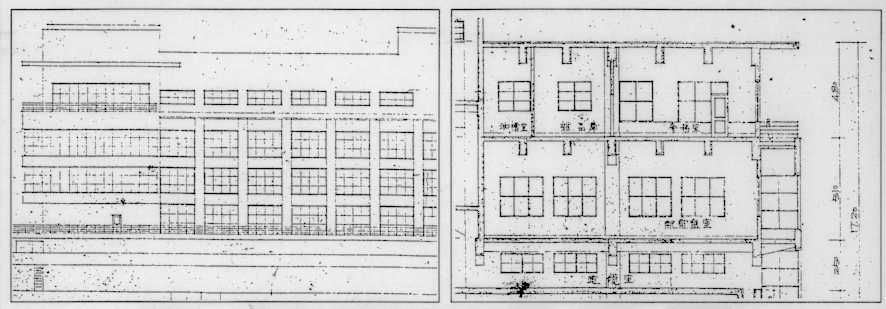 ●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図
●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図
- ・
ファサードにみられる規則的なリズムにより、モデュールの存在が直感できる。
- ・
平面図を見ると全てが規則的なモデュールに依るものではないことがわかる。桁行方向のスパン割りは9mを基本にシンメトリーに構成され、両端部で大きくなっている。
・
ファサードの構成を、立面図及び断面図の詳細な寸法により追いかけていくと、900㎜のモデュールが意識されていることが想像できる。
- ・ 建物の全てが900
モデュールで構成されているわけではなく、特に階高は内部の用途により不規則に定められており、ファサード表現時における処理の苦労が窺われる。
-
◎仮説Ⅱ:グリッド上での思考
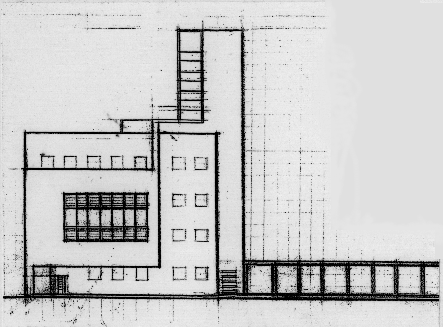 ●市民会館のスケッチ
●市民会館のスケッチ
- ・ 分離派建築会第5回展覧会(1926年)に出品された市民会館案のために描かれたスケッチを見ると、グリッド上での思考によりデザインを展開させていたことがわかる。
- ・
まず最初に1mグリッドが引かれ、その上に、あるボリュームをイメージした線が描かれたものと思われる。
- ・
概ねの線は、基本的にグリッドの上をなぞるように描かれている。
- ・ さらに、グリッドから1/2、1/3…と移動した位置にも線が引かれている。
- ・
このようにして引かれた線のうち、プロポーションの検証やボリュームをイメージしていく思考過程の中で不必要と判断された線は消され、重要な線はその上に何度も重ねて線を引くことにより強調されたようである。
◎仮説Ⅲ:プロポーションの決定方法
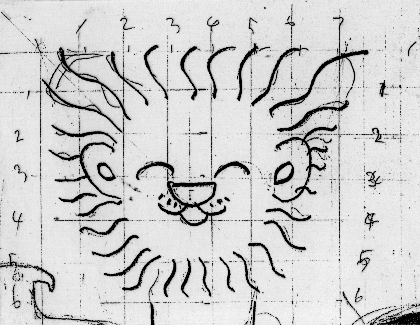 ●ライオンのスケッチ
●ライオンのスケッチ
- ・ 1963年頃のスケッチブックの中には、グリッド上での思考によるデザイン表現が数多くみられる。
- ・
グリッドに座標が記入されているものが多い。
- ・
上のスケッチはその典型と思われるが、グリッドはその上に線が描かれることを前提 にしているわけではなく、輪郭、目や鼻の位置などのプロポーションを検証し決定する ための座標であることがわかる。
- ・
ここに山口文象の建築観、自然観(世界観)の一部が見られるように思われ、重要な研究テーマとして今後も継続して対象としたい。
◎仮説Ⅳ:水平線に挟まれるボリュームの表現
●黒部川第二発電所の立面図・断面図
- ・
黒部川第二発電所は、実現案に至る前の計画案として、4つの外観パースが残されている。上のパースはそのうちの3つである。
- ・
4本の水平線が強く意識されていることが、上の4案に共通している。下から1本目は水面、2本目は堰堤、3本目は地階(1階)床面、4本目は4階床板(屋根)である (図参照)。
- ・
3本目と4本目に挟まれる1~3階の部分、そして4本目の水平線の上部である塔屋、この2つのボリュームの表現が、建物全体のデザインを決める上で大きなウエイトを占めるものとなる。
- ・
4つの案においては、1~3階のファサード及び塔屋の表現についての思考が繰り返し行われたものと思われる。
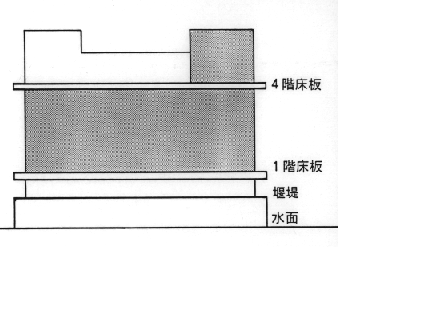
(2)スケッチ復元の作業手順
| ①グリッドの設定
|
②輪郭の記入 |
③水平線の強調 |
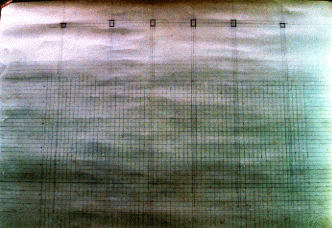 |
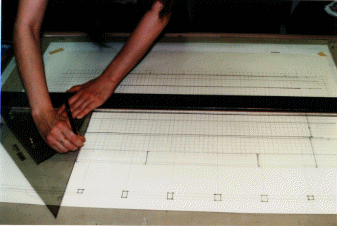 |
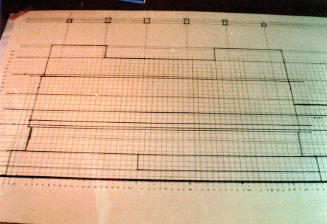 |
| ④ファサード表現の記入 |
⑤不要線の消去 |
⑥重要線の強調 |
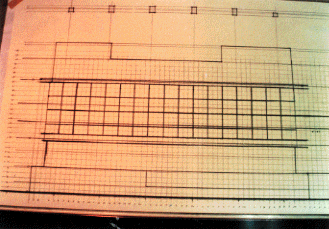 |
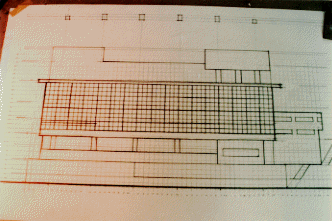 |
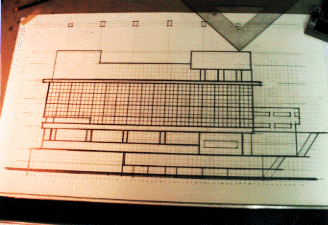 |
前ページに戻る
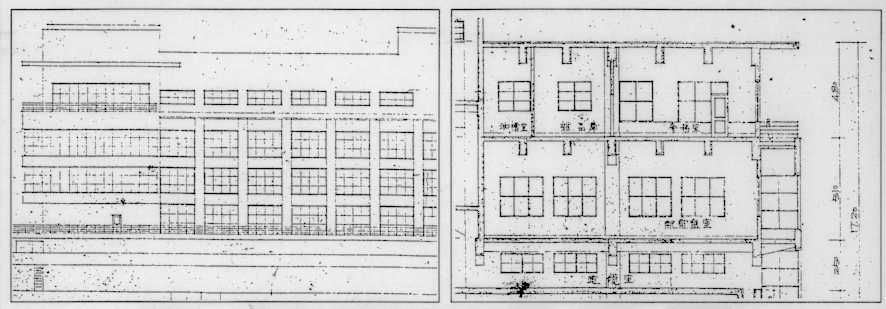 ●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図
●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図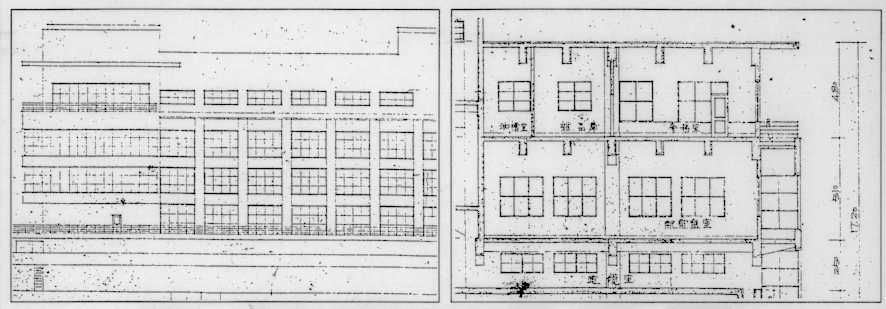 ●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図
●黒部川第二発電所改修時の立面図・断面図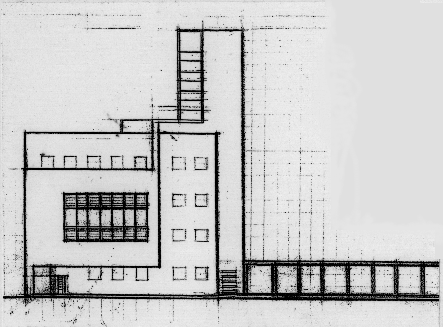 ●市民会館のスケッチ
●市民会館のスケッチ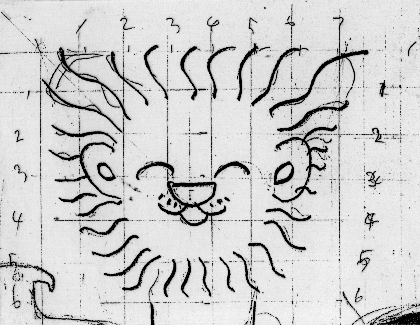 ●ライオンのスケッチ
●ライオンのスケッチ