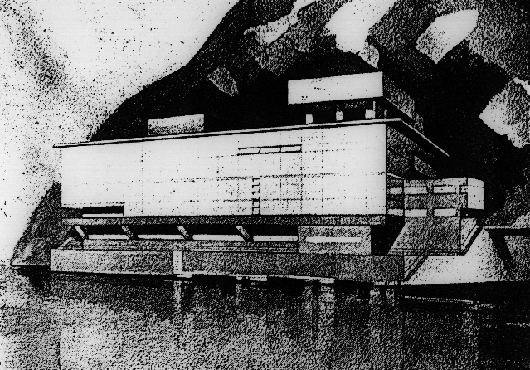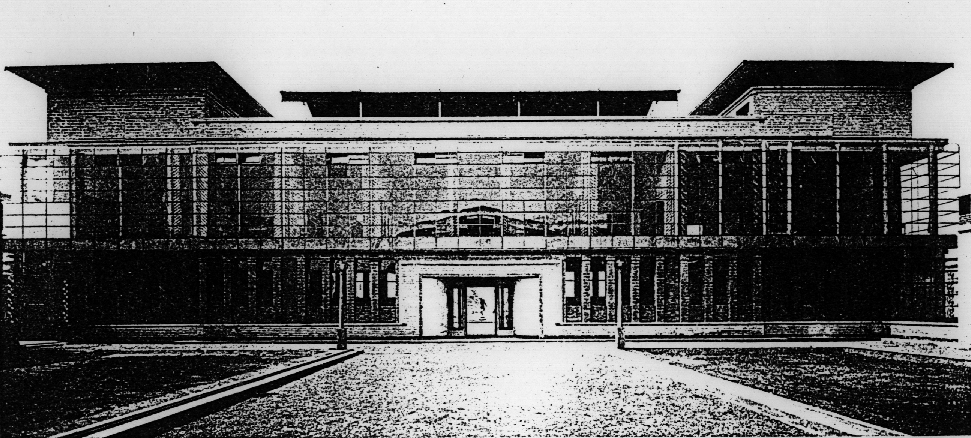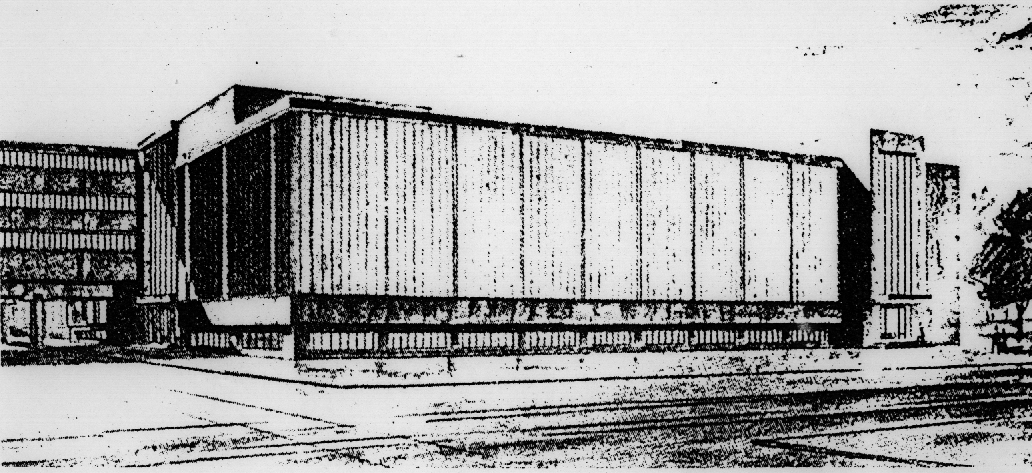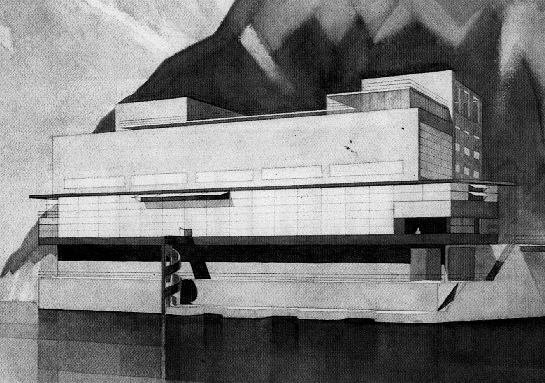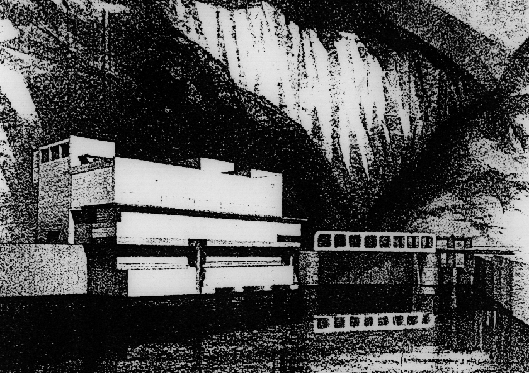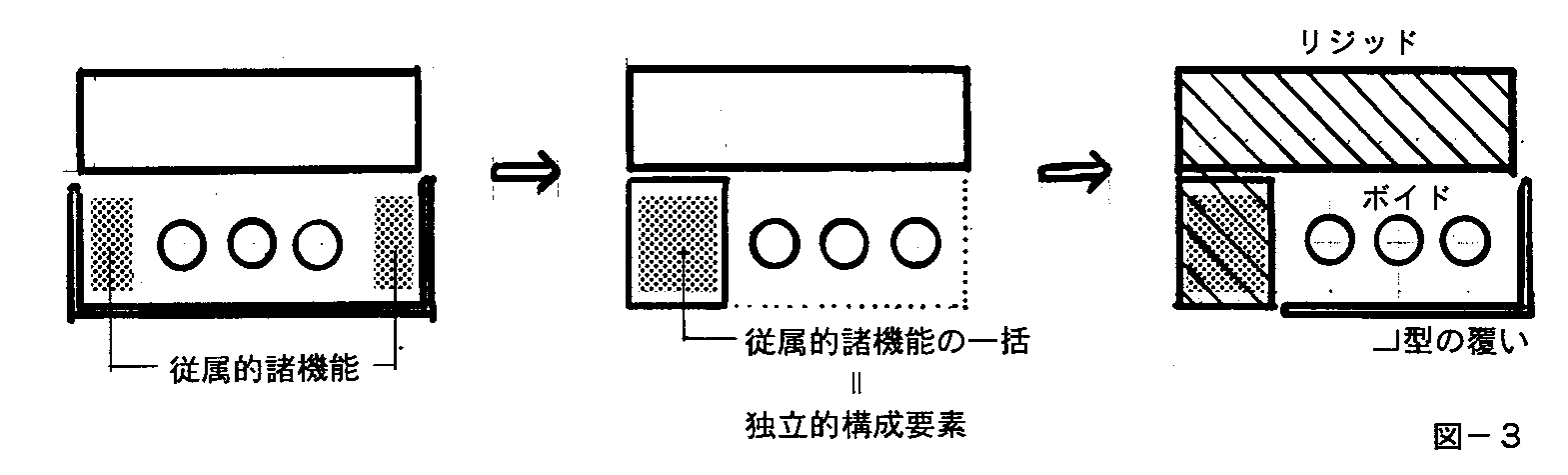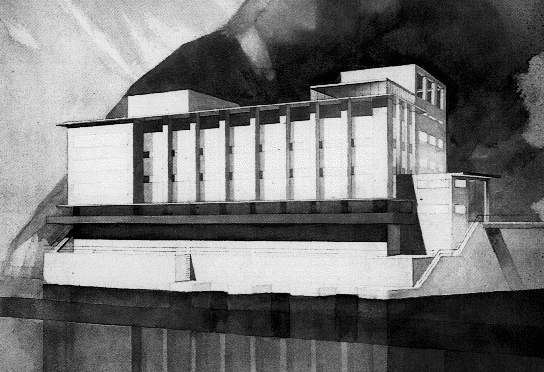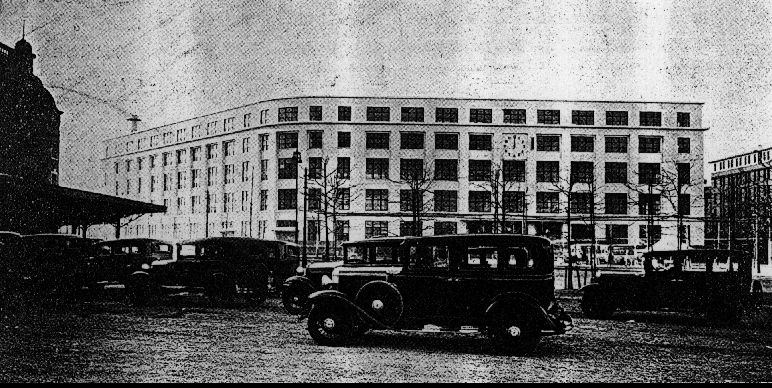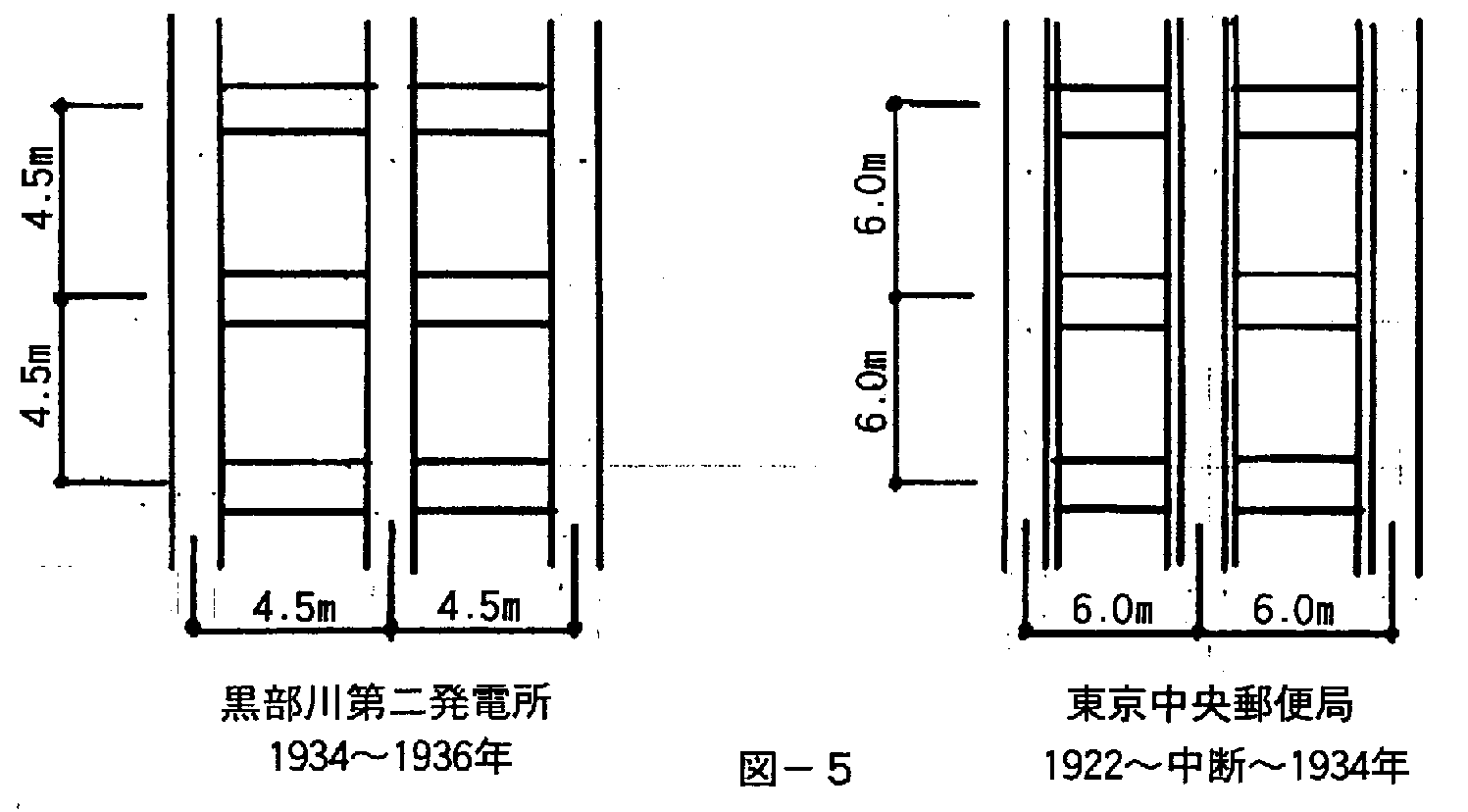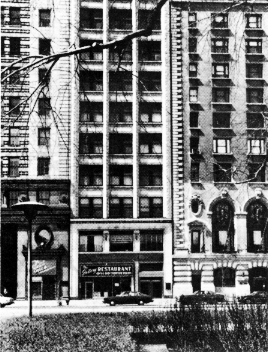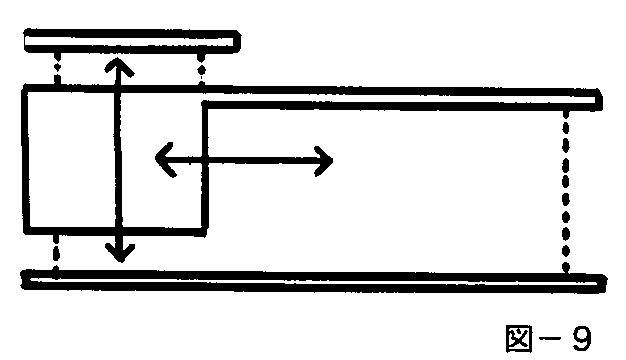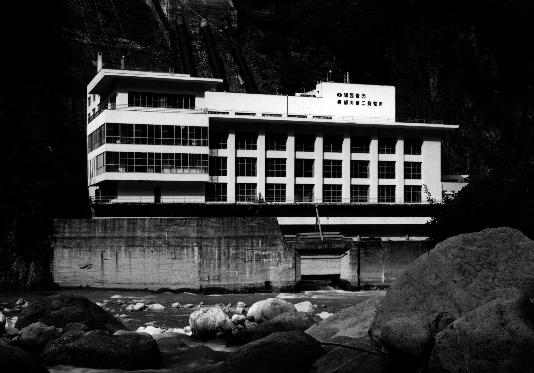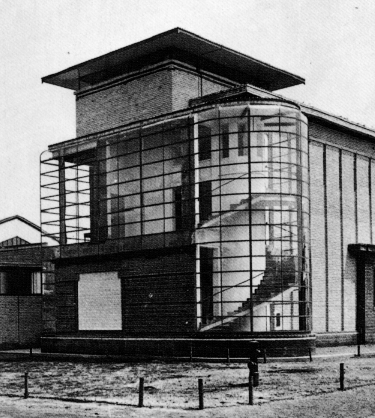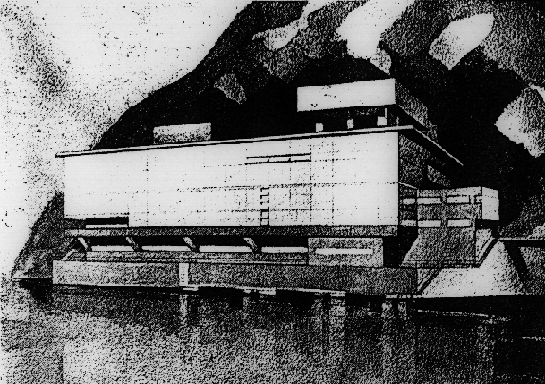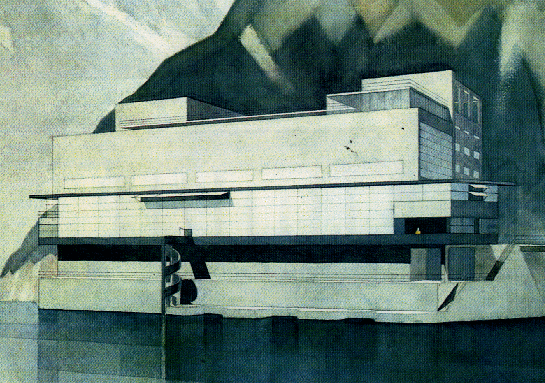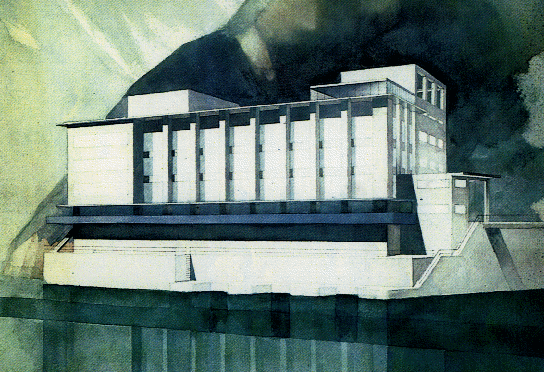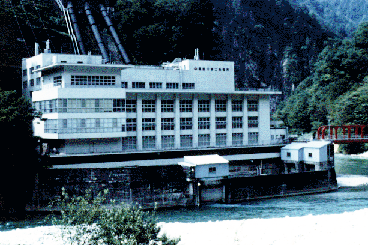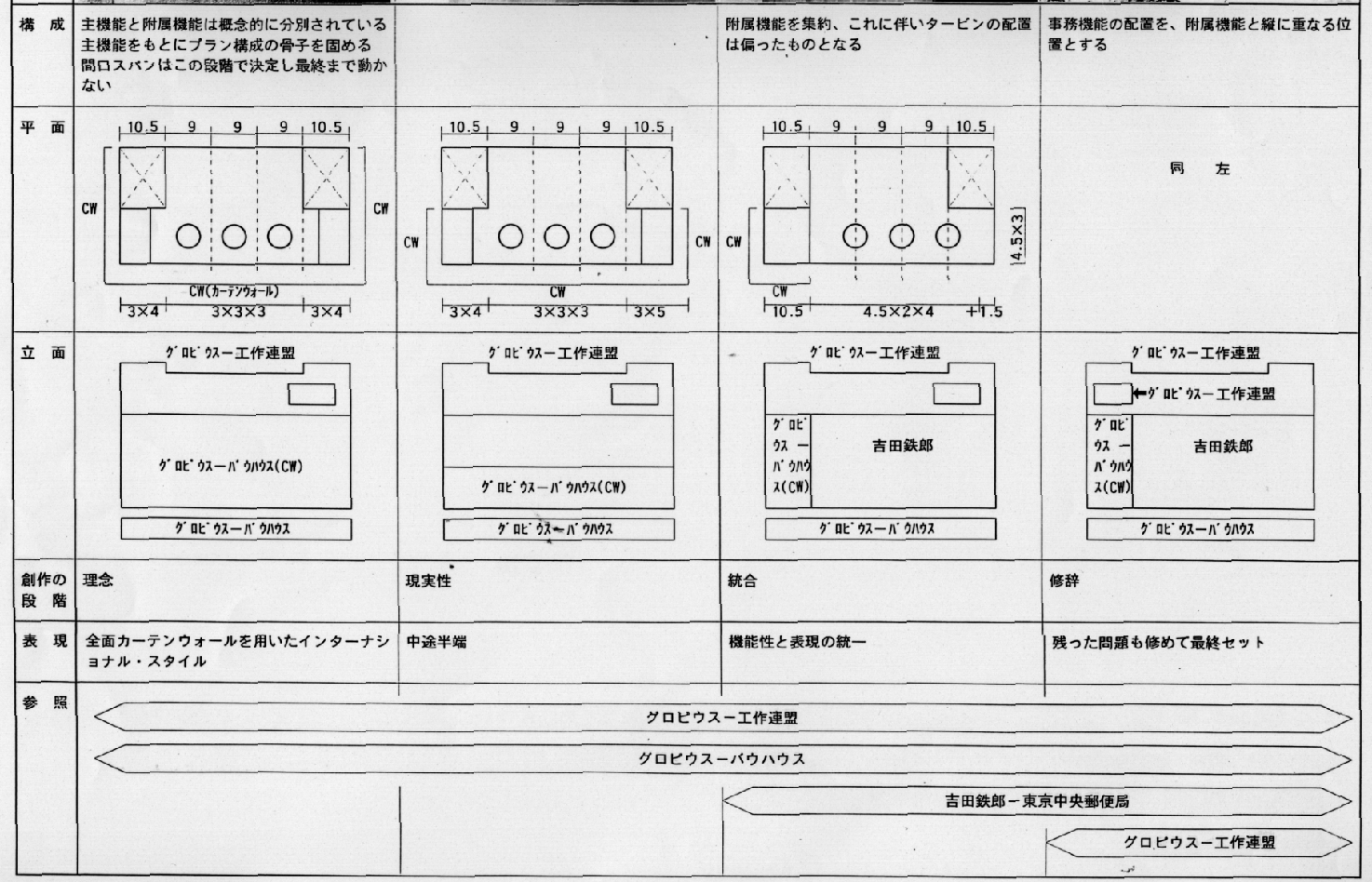| ◎ステップ3(最終的計画案) この段階では、諸機能がほぼ整理されたものと考えられる。
従属的諸機能は一括され左側にまとめられる。3基の発電機は、スパン中央の配置から柱軸に重なる配置へと変化している。母線室が右側でなく左側に配置された理由としては、右側に設けた場合に搬入動線との関係から母線室の必要長さが確保できないためと考えられる。このとき、整理一括された従属的諸機能の空間は、プラン構成上、主機能空間と同格の独立的要素となり、ステップ1~2とは異なる構成概念によって整理し直す必要が出てくる。
ここでさらに推測を深めると、「L型に固められたいわばリジッドな部分に対して、発電機置場をボイドな大空間と見倣すこと」が、新たな空間構成概念であると考えられる。住宅におけるサンルームのような意識でこの吹抜け大空間を捉えると、そのL型の覆いは当然他の部分と異なる表現が要求される(図-3)。この要求への対応として、カーテンウォールを採用することが最も素直な手段と考えられる。しかし、その大々的な使用は、施主サイドの意向により難しかったため、発電機室をL型に覆うフレームワークが登場したものと考えられる。これによってカーテンウォールは、独立的要素となった従属的諸機能群の立面に控えめに存続することとなった。
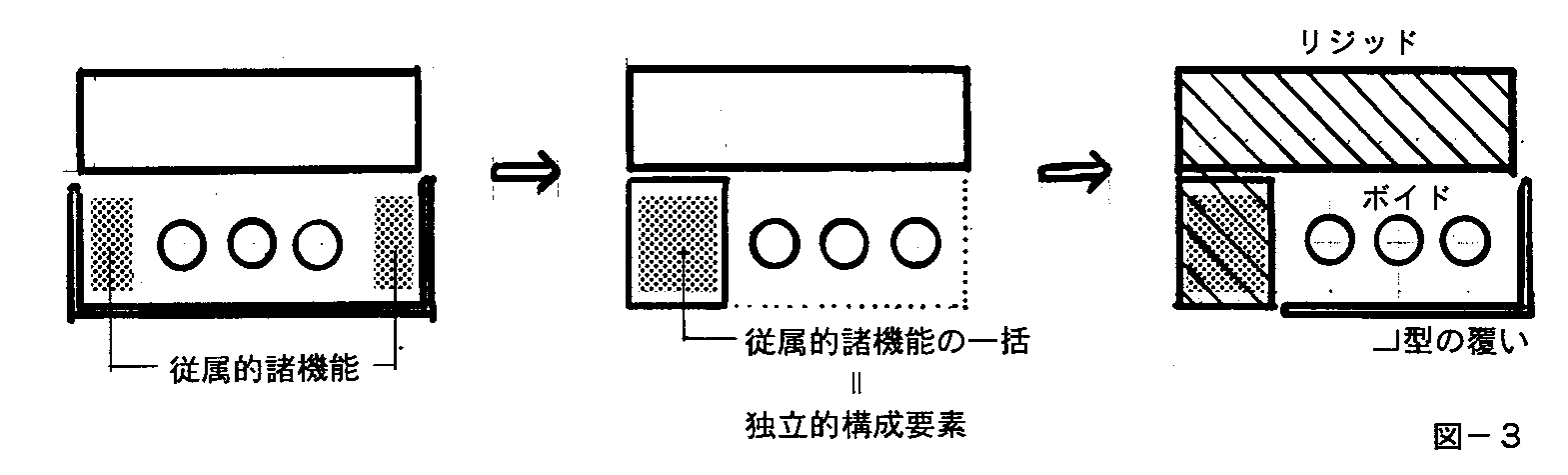
このフレームワークのモチーフが何に由来するかは明らかではない。ただ、吉田鉄郎の設計になる東京、大阪の両中央郵便局との明らかな近似を見ることができる(図-4)。
東京中央郵便局は、もともと武富英一によって設計され(このとき山口文象は製図とパースを担当した)、関東大震災のため中断されたものを吉田鉄郎が手直しし、現在の形で竣工している。武富英一の立面はウィーン歴史主義のルネサンススタイルの影響下に設計されていて、その装飾をはぎ取って近代的な姿に手直ししたものが今の外観であり、後述するように山口文象によると、吉田鉄郎のオリジナリティはその後に設計された大阪中央郵便局にあるという。
東京中央郵便局は柱芯-柱芯のヨコ寸法とタテ寸法の比が1:1のプロポーションを成しているが、黒部川第二発電所も同様のプロポーションを有している。両者の異なる点はルネサンスの名残である柱脇の袖壁の有無であり、東京中央郵便局からこの袖壁を取り去ると、両者の窓のプロポーションは一致する(図-5)。
ところで、1930年代に入る頃から、欧米諸国においてモニュメンタリティのある硬質な表現が時代的な傾向として見られるようになる。それらはいわゆる社会主義リアリズムやナチのモニュメンタリズムのような極端な擬古典主義をその典型とするが、それ以外に合理主義的な古典主義として見い出される例もあった。
黒部川第二発電所におけるフレームワークは、吉田鉄郎の2つの中央郵便局とともに、この上に述べた時代傾向に重なり合う部分をも持っているとすることは、この時代の世界的な時代背景を考えるとき必ずしもうがち過ぎた見方でもないものと思われる。この案が山口文象自身が非常に良くないと思っていたと自懐していること、日電社長に気に入られた案であることを考え併すと興味深いところである。
黒部川第二発電所と東京中央郵便局の両者を注意深く見比べると、最上部(中央郵便局ではプロポーション外の屋階を除いた部分)に造形処理上の相違がみられる。中央郵便局では、スパンドレルと柱型は櫛形に連続している。これは武富英一によるルネサンスの名残であろうが、その櫛形の意味するものは、ルネサンスから装飾が剥ぎ取られたことにより力強さが増した点である。装飾を欠いた櫛形は、上述した合理主義的な古典主義と共通する表現となっている(図-6,7)。
一方、黒部川第二発電所の場合は、最上部のスパンドレルも柱に対して他と同じ深さで納められており、凸状の柱を最上部で見切るものは、十分に突出した庇である。柱型がスパンドレルに優先する点は古典主義といえるが、そのフレームワークの表現は基本的には単なる合理主義に留まっており、シカゴ派のスケルトン・アーキテクチュア(グリッド・エレベーション)にむしろ近いものである(図-8)。
また、この立面は基壇を礎として立ち上がっているのではなく、建物を浮き立たせる水平処理の上に成り立っている。したがって、そのフレームワークにおいては柱よりもグリッドの概念が優先している。
|